映画批評「ホワイト・プラネット」
2006.4.21 映画批評

6月24日公開の「ホワイト・プラネット」の試写&監督ティーチイン。
監督:ティエリー・ラゴベール、ティエリー・ピアンタニダ 脚本:ティエリー・ラゴベール、ティエリー・ピアンタニダ、ステファン・ミリエール ナレーション:ジャン・ルイ・エティエンヌ 音楽:ブリュノ・クレ 上映時間:83分 配給:2006年仏・カナダ/東北新社、コムストック オーガニゼーション
北極に生きる動物たちの生活を追ったスペクタルドキュメンタリー。
時速100kmのブリザードが吹きすさぶ極寒期には−50℃にもなる北極圏。都会に生きるわれわれには想像すらできない氷の惑星(ホワイト・プラネット)の光景を収めた映像は、新鮮、驚き、衝撃、感動の連続である。
愛情に満ちたホッキョクグマの子育てをはじめ、100日をかけて約1000kmの道のりを歩くカリブーの群れ、メスをめぐり牙を交えるイッカク、氷を海を慎重に進むホッキョククジラ、縄張りをめぐっての壮絶な戦いをくり広げるジャコウウシのボス…。
弱肉強食という自然界の掟のなかで、生けとし生きるものすべてが、懸命に命をつなごうとする姿は、本能をことごとく鈍化させてきたわれわれ都会人にとっては、まさしく“別惑星”の物語である。
映し出される映像は、食うか食われるかの厳しい局面ばかりではない。動物たちは、ときに嬉々とした表情で喜びのダンスを踊り、またときには、厳しくも温かい愛情を子供たちに注ぐ。愛嬌たっぷりの動物たちのしぐさやふるまいに、思わず相好を崩してしまうシーンも少なくない。
それにしても、動物たちの表情を極めて至近距離で収めていることに驚かされる(撮影中、ホッキョクグマとスタッフの距離が20mというニアミスもあったという)。数年にわり回され続けたカメラは、通り一遍のアングルだけではなく、たとえば——ホッキョクグマの巣穴や、微細なプランクトンが泳ぐ海底——にまでおよび、みごとに臨場感を勝ち取っている。わずか90分弱の作品を作り上げるためにスタッフが費やした時間と労力とリスクは、フィクション映画と同等に語れる類ではない。
試写後のティーチインで、ティエリー・ピアンタニダ監督は、貴重な映像の数々いついて「撮影は動物たちとアポイントをとるかのように行われた」と語った。日本の約80倍あるという広大な大地で、雑多な動物たちの決定的な瞬間を“偶然に”捉えることはよもや不可能。それらの撮影を成功させるには、北極圏の生態系調査を含め、慎重かつ綿密に準備を進めなければならなかったという。
エピローグでは、北極圏にじわじわと忍び寄る破壊の危機がナレーションされた。一説には今世紀中にも消滅してしまう可能性もあるという北極。温暖化をはじめとした人間の手による環境破壊のツケを、極めて厳かに生きる北極圏の動物たちが背負わされているという事実は、人間に対する警告として真摯に受け止めなければなるまい。
映画的なことを言うならば、BGMがやかましすぎる点が大きなマイナス。テーマとも映像ともそぐわない大味な音楽が、せっかくの貴重なフィルムに水を差している。それと、ホッキョクグマの出産シーンが、実は動物園で撮影されたというのはどうなのだろう……(ティーチインで監督が告白)。新たな生命の誕生という重みは変わらないとはいえ、あたかも北極で撮影されたかのような編集にはいささか疑問を感じた。
とはいえ、本作「ホワイト・プラネット」が、かけがえのない地球に対するオマージュとして異彩を放っているのは事実。その声を聞き取るのは、耳ではなく、心であるべきなのだろう。
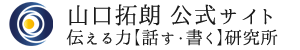
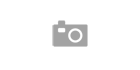
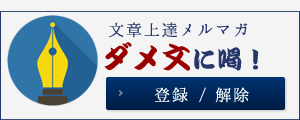
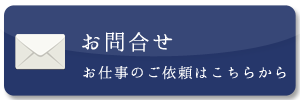
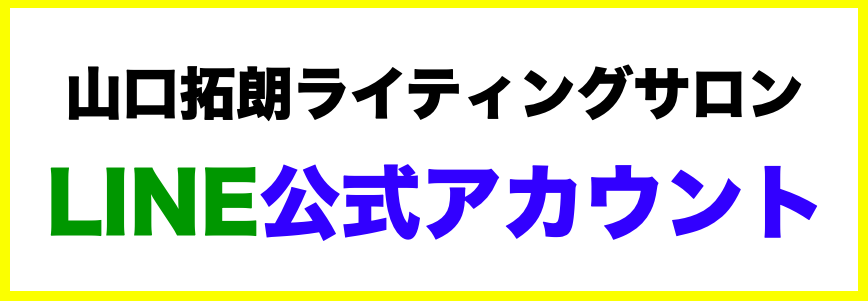





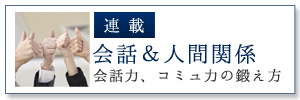
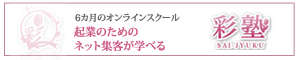

記事はお役に立ちましたか?
以下のソーシャルボタンで共有してもらえると嬉しいです。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓